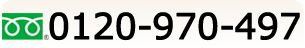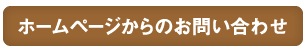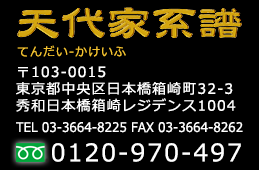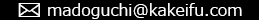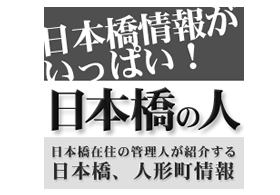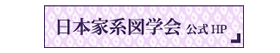松江城(国宝・史跡) -島根県松江市-
2025 / 04 / 20 歴史コラム
目次
-
-シェア
松江城は、別名「千鳥城」とも呼ばれ、日本に現存する12天守の一つであり、国宝指定された5城(松江城の他は、犬山城、松本城、彦根城、姫路城)の中では、国宝指定が平成27年(2015)と最も遅い城です。築城は慶長16年(1611)、堀尾忠氏によるものですが、山陰地方の政治経済の中心となる藩庁としての役割を担っていました。藩主は堀尾→京極→松平と変わりますが、寛永15年(1638)出雲18万6千石で入封した松平直政から明治維新まで続きました。城の構造は、輪郭連郭複合式平山城で、松江の水郷を生かした縄張りで、日本三大湖城(松江城の他、膳所城、高島城)の一つにも数えられます。桜の名所でもあり、水郷を巡る遊覧船、城下町の面影の残る塩見縄手など、松江市の観光名所となっています。
撮影日2024年04月12日