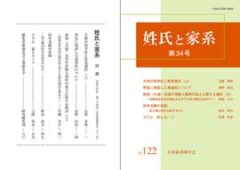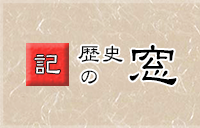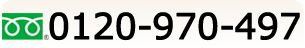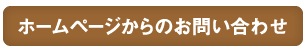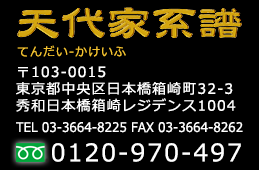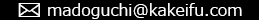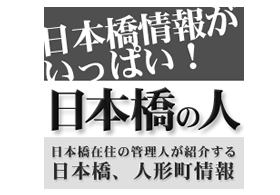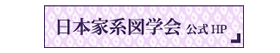歴史コラム
-
2026.1.20 歴史コラム 十勝牧場 白樺並木 – 北海道河東郡音更町
十勝牧場 白樺並木は、音更町の「美林」に指定されています。十勝牧場入口から直線で約1.3km続く白樺並木は、今から約70年前牧場職員の手で植樹されました。映画『雪に願うこと』やドラマ『マッサン』など、数々の作品のロケ地ともなり、北海道らしい絶景として知られます。白樺並木は見学自由ですが、車両の通行もあり見学の際は注意が必要です。牧場内の牧草地、施設等は立入禁止となっており、売店やごみ箱はありませんので、見学したら移動しましょう。
2025.12.20 歴史コラム 仁科神明宮(国宝)– 長野県大町市社宮本仁科神明宮(にしなしんめいぐう)神明宮は、皇大神宮御領であった仁科御厨の鎮護のため、この地方の支配者 仁科氏によって、伊勢神宮内宮が勧請され創建されました。以来、1000年以上にわたり20年に1度の式年造営が行われてきました。現在の建物は江戸時代のはじめのもので、わが国古来の「神明宮」の様式を正確に伝えていることから、本殿、釣屋、中門は国宝に指定されています。参道脇の大杉をはじめ、スギ、ヒノキなどが茂る境内や社叢は、県の天然記念物に指定されています。
2025.12.11 歴史コラム 日本家系図学会誌「姓氏と家系」第34号 発行日本家系図学会誌「姓氏と家系」令和7年-2 第34号(会誌通巻第122号)が発行されました。
発行日 令和7年12月10日<目次>
・大和の筒井氏と乾党諸氏(上) ‥ 宝賀寿男
・甲斐に残留した南部氏について ‥ 真野信治
・南部(大浦)光信の津軽入部時の従士に関する検討(5)
~津軽為信の出自検討および下久慈の検討も併せて~ ‥ 岩城大介
・田中光顕の系図
─安土桃山時代以前を中心に─ ‥ 松永昂大
・コラム 旅…2025.11.20 歴史コラム 金鳳山平林寺(天然記念物・名勝)– 埼玉県新座市野火止金鳳山平林寺(きんぽうざんへいりんじ)は、臨済宗妙心寺派の修行道場で、伽藍の囲む境内林は武蔵野の雑木林の面影を残すものとして、国の天然記念物に指定されています。 岩槻にあった平林寺は、寛文3年(1663)松平信綱の遺命によって、現在の野火止の地に移されました。徳川家康の関東入部に伴い、家臣として上京した大河内秀綱は、平林寺の大檀那でしたが、秀綱の孫で松平家の養子となった松平伊豆守信綱は、三代将軍家光、四代将軍家綱のもとで幕府老中を務めました。その一族は代々大河内松平家廟所で供養され、平林…
2025.10.19 歴史コラム 高岡山瑞龍寺(国宝) – 富山県高岡市 高岡山瑞龍寺は曹洞宗の寺院で、加賀藩二代藩主前田利長の菩提をとむらうため、三代藩主利常によって建立さました。前田利長は慶長14年(1609)高岡城を築城しましたが、利長は慶長19年(1614)この地で亡くなりました。加賀百万石を譲られた義弟利常はその恩を深く感じ、名匠山上善右衛門嘉広により七堂伽藍を完備し、広山恕陽禅師をもって開山としました。造営は正保年間から、利長の五十回忌の寛文3年(1663)まで約20年を費やしました。寺は、周囲に壕をめぐらし、城郭を想わせるものがあっりました。江戸初期の禅…2025.9.20 歴史コラム 独股山前山寺(重要文化財) – 長野県上田市前山前山寺(ぜんざんじ)は、真言宗智山派の古刹で、塩田平を見下ろす独鈷山麓に佇む霊場です。本尊は大日如来、間口十間、奥行八間の木造萱葺の本堂は、元禄11年(1698)~享保12年(1727)の創建と推定されます。弘仁年中(812)空海上人が護摩修行の霊場として開創したと伝えられ、元弘年中(1331)讃岐国善通寺より長秀上人が来止し、正法院を現在の地に移し、前山寺を開山したといわれます。境内に建つ三重塔(国指定重要文化財)は、室町時代の建立とされ、三間三重で、高さ19.5m、屋根は柿葺です。二…
2025.8.20 歴史コラム 川中島古戦場(川中島古戦場八幡社) – 長野県長野市小島……上杉謙信と武田信玄が戦った、川中島第四次合戦で、この八幡原に武田軍の本陣があったと伝えられます。現在はここに八幡社や市立博物館が設けられ、周辺は川中島古戦場史跡公園として整備され、歴史散策や市民の憩いの場となっています。武田信玄が本陣を置いたとされる川中島古戦場・八幡社には、「一騎討ち像」「三太刀七太刀之跡の石碑」「執念の石」「首塚」「逆さ槐」が置かれ、当時をしのぶことができます。
2025.7.20 歴史コラム 鼠ヶ関(鶴岡市指定史跡) – 山形県鶴岡市鼠ヶ関鼠ヶ関(ねずがせき)は、奥羽三関の一つで、越後国と出羽国の国境に位置し、出羽国の日本海側の玄関口となっていました。奥羽三関とは、五世紀頃に蝦夷の南下を防ぐために設けられた関所で、鼠ヶ関の他、勿来関(福島県いわき市)、白河関(福島県白河市)を指します。
「鼠ヶ関」の文献上の初見は、平安時代中期の歌人・能因法師の「能因歌枕」で、「ねずみが関」とあります。その他、「保元物語」には「念誦の関」、「義経記」には「念珠の関」、「吾妻鏡」には「念種関」と記されています。
…2025.6.20 歴史コラム 長者ケ原遺跡(国指定史跡) – 新潟県糸魚川市大野長者ケ原(ちょうじゃがはら)遺跡は、姫川河口近くの台地上に縄文時代早期から後期まで営まれてきた遺跡で、現在遺跡公園として整備されています。糸魚川でしか産出されないヒスイの産地でもあり、糸魚川市立フォッサマグナミュージアムに隣接しています。竪穴住居、掘立柱建物などが復元展示され、土器捨て場展示施設では、土器や石器が出土したようすをガラスごしに見ることができます。この場所からは多量の土器が出土しており、土器のほかにもヒスイ原石や蛇紋岩の石斧の未成品、また玉類の製品や完全な形の指輪形石製品とい…
2025.5.20 歴史コラム 扇谷上杉家糟屋館跡(伊勢原市指定史跡) - 神奈川県伊勢……糟屋館(かすややかた)は、相模国守護・扇谷上杉氏の本拠地で、「上杉館跡」として伊勢原市の史跡に指定されており、扇谷上杉家の家宰・太田道灌が暗殺された場所として知られています。糟屋館の周辺は、現在産業能率大学になっており、新東名高速道路の工事などもあって、地形は大きく変わりつつあり、そのうち大学前の糟屋館の説明板以外、跡形もなくなくなると思います。太田道灌の胴塚は、上粕屋の曹洞宗の寺院洞昌院にあります。伝説では、道灌は襲撃を受けた後この寺まで逃れ、この時山門が閉まっていたため、ここで自決を…