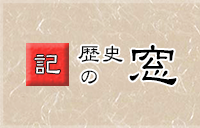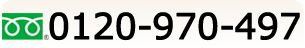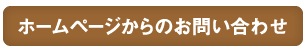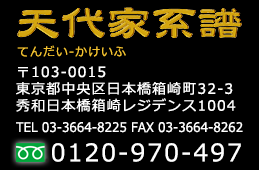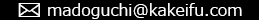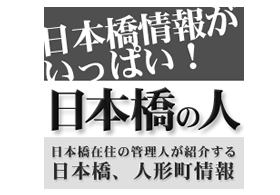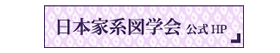歴史コラム
-
2022.8.20 歴史コラム 比企城館跡群 菅谷館跡(国指定史跡) -埼玉県嵐山町菅谷……
菅谷館跡は、国指定史跡 比企城館跡群(菅谷館跡・杉山城跡・小倉城跡・松山城跡)の中核を占める遺跡で、鎌倉時代の武士 畠山重忠の居館と伝えられます。埼玉県立嵐山史跡の博物館が併設されており、この地方の中世史を学ぶことが出来ます。
畠山重忠は、長寛2年(1164) 武蔵国男衾郡畠山郷(深谷市)の地に生まれたといわれています。宇治川の合戦、奥州攻めなどで戦功があり、鎌倉の有力御家人で、鎌倉幕府創業に功績がありました。元久2年(1205) 北条氏の策略により二俣川(神奈川県横浜市旭区)で…2022.7.20 歴史コラム 新井城址(神奈川県史跡) -神奈川県三浦市三崎町小網代-新井城址は神奈川県三浦市にある城跡で、相模三浦氏の居城でした。小網代湾と油壺湾に挟まれた岬状の台地で、岬の先端は現在油壷マリンパークとなっており、過去に凄惨な籠城戦があった城跡だったことは想像することもできません。
三浦氏は相模国三浦郡を本拠地とする武士団で、古くから源氏との結びつきが強く、鎌倉幕府では有力御家人でしたが、その勢力が執権北条家を凌ぐほどになったため、宝治元年(1247)の宝治合戦で北条氏と安達景盛らによって滅ぼされました。その後、傍流の三浦盛時(佐原氏)により再興…2022.6.20 歴史コラム 永福寺跡(国指定史跡) -神奈川県鎌倉市二階堂-永福寺(ようふくじ)は、源頼朝が文治5年(1189)に奥州合戦の後、戦いで亡くなった数万の将兵の鎮魂のために建てたれた寺院で、平泉の毛越寺や中尊寺を参考にしたとされています。頼朝が征夷大将軍に任命された建久3年(1192)二階堂が完成し、この堂の名は現在の地名ともなっています。建久5年(1194)までに、阿弥陀堂、薬師堂が完成し、この三つの堂を中心に、惣門、南門、釣殿、多宝塔、鐘楼、僧坊などの建物があったとされ、「その姿形は極楽の様子をそのまま表したようだ」と形容されています。二階堂の本…
2022.5.20 歴史コラム 林芙美子記念館 -東京都新宿区中井-林芙美子記念館は、「放浪記」「浮雲」などの代表作で知られる作家・林芙美子が、晩年に住んでいた家です。
芙美子は山口県下関生まれといわれ、家庭環境は複雑で、九州を転々としながら幼少期を育ち、大正5年(1916)に広島県尾道市に移り、女学校を卒業しました。大正11年(1922)に上京した芙美子は、様々な職業を経験し、男性遍歴も多く、作品を雑誌・出版社に売り込んで回りました。昭和元年(1926)、手塚緑敏と内縁となり、昭和3年(1928)から小説「放浪記」を連載し好評を得ました。昭和5…2022.4.20 歴史コラム 松本城(国宝・史跡) -長野県松本市-松本城は、現存する五重六階の天守の中で日本最古で天守は国宝に指定されています。黒を基調とした引き締まった姿は、背景の北アルプスの山々によく映え、見事な景観を見ることが出来ます。
松本城は、永正年間(1504-1520)信濃守護小笠原氏が林城を築城し、その周りを取り囲むように支城が構えられ、その一つとして深志城が築城されたのが始まりといわれています。
その後甲斐の武田信玄に小笠原長時が放逐され、信濃支配の拠点としましたが、 天正10年(1582)本能寺の変の混乱に乗じて、…2022.3.20 歴史コラム 長久手古戦場(国指定史跡) -愛知県長久手市武蔵塚-長久手古戦場は、天正12年(1584)に羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)と徳川家康が熾烈な戦闘を繰り広げた主戦場跡で、国の史跡に指定されています。現在、この場所は「古戦場公園」として整備され、園内には武将の塚や郷土資料室が設けられています。ここから約1Km北にある「色金山歴史公園」には、家康が合戦時に腰掛けて軍議を開いたといわれる床几石が残されています。
小牧・長久手の戦いは、天正12年(1584)3月にはじまりました。秀吉軍と家康・信雄連合軍は、しばらく小牧でにらみ合いましたが、秀吉軍は…2022.2.22 歴史コラム 源頼朝上陸地〔千葉県指定史跡〕 -千葉県鋸南町勝山-石橋山の戦いで敗れた源頼朝は安房勝山に逃れますが、この地の豪族 安西景益は頼朝側につき自分の館に招き入れました。安西氏は千葉常長の二男常遠が安西四郎を称したといわれます。安西氏が築いたといわれる勝山城は千葉県安房郡鋸南町の勝山港を見下ろす八幡山にありました。中世の典型的な海城で、安西氏が出城として築いたのがその始まりといわます。その後、里見氏が一体を支配するようになると、この地は500艘ともいわれる里見水軍の本拠地となりました。江戸初期に里見氏が滅亡した後は、内藤氏、佐倉氏の居城となり、…
2022.1.20 歴史コラム 高山市三町〔重要伝統的建造物群保存地区〕 -岐阜県高山市……三町(さんまち)は岐阜県高山市中心部の古い町並みで、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。
この街を築いたのは、初代飛騨高山藩主 金森長近。当時この地を支配していた三木氏を滅ぼし、天正14年(1586)飛騨国3万3千石の領主となりました。長近は、天神山古城(現在の城山)に飛騨高山城を築き、同時に城下町を整備しました。高台を武家地、一段低いところを町人町としました。また、東側には寺社を移築・建立しました。
金森氏の統治は6代107年間続きましたが、元禄5年(1…2021.12.20 歴史コラム 雲巌寺〔禅宗四大道場〕 -栃木県大田原市雲岩寺-雲巌寺(うんがんじ)は、栃木県大田原市雲岩寺にある臨済宗妙心寺派の寺院です。山号は東山、越前の永平寺(福井県永平寺町)、紀州の興国寺(和歌山県由良町)、筑前の聖福寺(福岡県福岡市博多区)とともに、日本の禅宗四大道場との一つです。松尾芭蕉も訪れ、「木啄も 庵はやぶらず 夏木立」と句を残しています。
開山は、弘安6年(1283)鎌倉円覚寺開山仏光国師の弟子 高峰顕日(仏国国師)といわれます。兵火や火災の被害に遭いながらもその都度再建され、現在まで禅道場としての威厳が保たれてきました。…2021.11.20 歴史コラム 南湖公園〔国指定史跡・名勝〕 -福島県白河市南湖-南湖公園(なんここうえん)は、寛政の改革で知られる12代白河藩主 松平定信によって享和元年(1801)に築造された日本最古といわれる「公園」です。大正13年(1924)に「南湖公園」として国の史跡・名勝に指定されました。
定信は、「士民共楽(武士も庶民も共に楽しむ)」という理念のもと、身分の差を越え、誰もが憩える地を造りました。また、「共楽亭」という茶室を建て、庶民と楽しみを共にしたと伝えられています。
「南湖十七景」は、定信が大名庭園に作られる「名所」と同様に、南湖の…