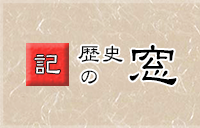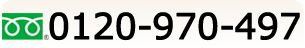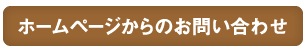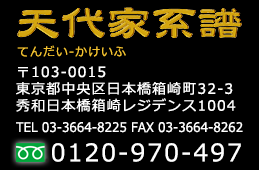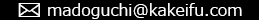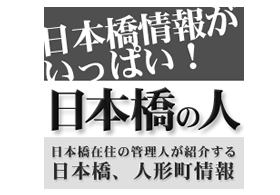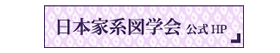歴史コラム
-
2021.10.20 歴史コラム 秋田城跡〔国指定史跡〕 -秋田県秋田市寺内焼山-
秋田城は、東北地方の古代城柵の一つで、律令国家のもと、蝦夷支配を目的に置かれた軍事・行政機関です。現在、発掘調査の成果をもとに、秋田城史跡公園として整備され、市民の憩いの場にもなっています。
秋田城は奈良時代から平安時代にかけて東北地方の日本海側(出羽国(でわこく))に置かれた大規模な地方官庁で、政治・軍事・文化の中心地でした。蝦夷(えみし)の人々が暮らしていた東北各地に同じように造られた律令国家の地方官庁の遺跡は「城柵官衙遺跡」(じょうさくかんがいせき)と呼ばれており、秋田…
2021.9.20 歴史コラム 堀越城跡〔国指定史跡〕 -青森県弘前市大字堀越-堀越城は、戦国時代末期、弘前藩初代藩主となる津軽為信により築城されました。弘前市では平成10年(1998)~25年(2013)まで発掘調査が行われ、その成果をもとに史跡公園として整備され、令和2年(2020)4月に全面公開されました。
堀越城跡の概要については、弘前市のHPに次のように紹介されています。
「堀越」という地名が文献上に現れるのは、南北朝時代の建武4(1337)年にさかのぼります。この時の記録には「堀越に楯(館)[たて]を築く」とありますが、この「楯…
2021.8.20 歴史コラム 前沢曲家集落〔重要伝統的建造物群保存地区〕 -福島県南会……福島県南会津町の前沢曲家集落は、曲家の統一した家並みが残されており、国の重要伝統的建物群保存地区に指定されいます。
13棟の建物は全て住居として使用されており、敷地内に入ることはできませんが、一棟が資料館となっており建物内が見学できます。
この集落は明治40年(1907)の大火で焼失しましたが、その後中門造りといわれる民家を、新しい工法で一斉に再建したため、曲家の統一した家並みが出現しました。
南会津地方の重要伝統的建物群保存地区には、大内宿(下郷町)のような…2021.7.22 歴史コラム 岩手・遠野 伝承園〔国指定重要文化財〕 -岩手県遠野市土……「遠野物語」で知られる遠野市ですが、「伝承館」は、民話と伝説の里、遠野自然と共に生きた人々の暮らしを垣間見る、この地方の農家の生活様式を再現し、伝承行事、昔話、民芸品の製作・実演などが体験できる施設です。
園内には、国の重要文化財に指定されている曲り家「菊池家住宅」、遠野物語の話者「佐々木喜善記念館」、千体のオシラサマを展示している「御蚕神堂」などがあり、郷土料理を堪能できるお食事処も備えられ、遠野観光の中心地の一つです。
近くには、「カッパ淵」、「たかむろ水光園」などもあり、…2021.6.20 歴史コラム 大湯環状列石〔特別史跡〕 -秋田県鹿角市十和田大湯-特別史跡 大湯環状列石(おおゆかんじょうれっせき)は、野中堂、万座に所在する二つの環状列石を主体とする大規模な縄文時代後期(約4000年前)の遺跡です。
二つの環状列石は、川原石を様々に組み合わせた配石遺構を二重の環状に配置した構造となっています。環状列石の最大径は、野中堂環状列石が44m、万座環状列石が25mで、それぞれの中心の石と「日時計状組石」と呼ばれる特殊な形状の組石が一直線に並ぶ位置関係にあります。
環状列石の周辺については、これまでの調査により、建物跡、貯蔵…2021.5.20 歴史コラム 美濃金山城跡〔国指定史跡〕 -岐阜県可児市兼山-美濃金山城跡(みのかねやまじょうあと)は戦国時代の城郭で、鬼武蔵といわれた森長可ら森氏の居城として知られています。木曽川と兼山町を見下ろす山上に築かれ、織豊系城郭の特徴である石垣、瓦、礎石が見られ、土木工事の技術の高さを示す削られた岩盤、また城の終焉を伝える破城の痕跡も残されています。
金山城は天文6年(1537)斎藤正義が築城し、烏峰城(うほうじょう)と名付けられました。永禄8年(1565)織田信長から森可成に与えられ、金山城と改称しまし。元亀元年(1570)近江宇佐山城の戦い…2021.4.20 歴史コラム 京極氏遺跡〔国指定史跡〕 -滋賀県米原市上平町-京極氏遺跡は、滋賀県伊吹山の南山麓にある戦国大名京極氏の城館遺跡です。京極氏は、近江佐々木氏の一族であり、南近江を領した一族の六角氏に対し北近江を領し、始祖氏信以来多くは山東町の柏原館を本拠としていました。一族の内紛を永正2年(1505)に収めた京極高清は、柏原館を廃し伊吹山南山麓の上平寺に新たに城館を築きました。以後、大永3年(1523)国人一揆により落城するまで、北近江の政治・文化の中心として機能してきました。
遺跡は、京極氏館跡、上平寺城跡、家臣団屋敷跡及び山岳寺院を軍事的に…2021.3.20 歴史コラム 埼玉古墳群〔特別史跡〕 -埼玉県行田市大字埼玉-埼玉(さきたま)古墳群は、5世紀後半から7世紀初頭にかけて築かれた古墳群で、前方後円墳8基、円墳1基、並びに小円墳群で構成されています。我が国屈指の古墳群で、国の特別史跡に指定されており、世界遺産への登録を目指しています。
古墳群は前方後円墳の形態に強い規格性を持ち、古墳時代の地域の首長層とヤマト政権とのつながりなど、古墳研究上、重要な遺跡として高く評価されています。
昭和43年(1968)、「さきたま風土記の丘」を整備するため稲荷山古墳を発掘調査したところ、人を埋葬した施設…2021.2.19 歴史コラム 白川郷〔世界遺産・重要伝統的建造物群保存地区〕 -岐阜県……白川郷は、岐阜県北部庄川上流にある集落で、合掌造りの家並みが独特の景観を形成しています。昭和51年(1976)重要伝統的建造物群保存地区に指定され、平成7年(1995)に、五箇山(富山県)と共に「白川郷・五箇山の合掌造り集落」として、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されました。
合掌造りの家屋は、耐震、防火、積雪など、この地方の自然環境と生活の知恵が生かされたものです。家屋の中では、一階は生活の場でしたが、上層は養蚕や機織りが行われていました。同じ建物の中で、生活と労働が集約…2021.1.20 歴史コラム 名古屋城〔特別史跡〕 -愛知県名古屋市中区-名古屋城は、名古屋市のシンボルで、天守に輝く金の鯱が有名です。日本100名城の一つにも数えられ、国の特別史跡に指定されています。
ここには16世紀後半、今川氏が築城した那古野城がありました。熱田台地の北西端に位置し、濃尾平野の軍事上の要衝にあたります。織田信長はここから清州に本拠地を移したため廃城になっていました。
関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、豊臣方への備えとして慶長18年(1609)にここに新城を築き、それまで城のあった清州から城下町を移しました。以後御三家筆頭…