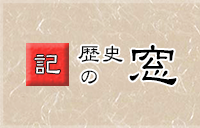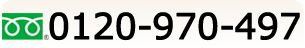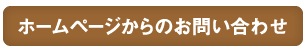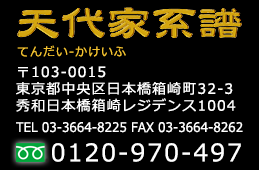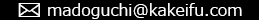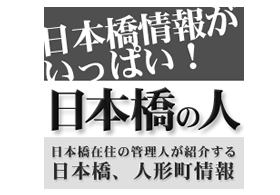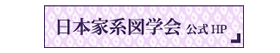歴史コラム
-
2024.5.20 歴史コラム 隠岐国分寺跡(史跡) ‐島根県隠岐郡隠岐の島町池田‐
隠岐国分寺跡は、隠岐に流された後醍醐天皇の行在所と伝えられています。現在この地にある隠岐国分寺(東寺真言宗)の後方に礎石があり、これが明治の廃仏毀釈前の本堂跡です。境内からは奈良時代の瓦が見つかっていますが、創建時の様子は分かっていません。毎年4月には重要無形民俗文化財の蓮華会舞がおこなわれます。現国分寺の境内は、昭和9年(1934)に遺跡の包含地として国の史跡に指定された。平成19年(2007)に本堂が火災により焼失しましたが、再建に伴い平成21年度(2009)から実施された発掘調査に…
2024.4.20 歴史コラム 躑躅ヶ岡(名勝) ‐群馬県館林市‐館林市のつつじが岡公園のあたりは、古代より野生のヤマツツジが群生する地で、江戸時代中期の絵図などには既に「躑躅ヶ崎(つつじがさき)」の名で記載されています。自生していたヤマツツジに加え、歴代の館林城主は各地よりツツジを移植し園の拡張や整備を行いました。主なもので、寛永4年(1627) 松平(榊原)忠次(ただつぐ)は、当時領内だった新田郡武蔵島村(現群馬県太田市)から、新田義貞の妻 勾当之内侍(こうとうのないし)のために植えたと伝えられるツツジを数百株を移植しました。また、寛文年間(166…
2024.3.20 歴史コラム 今帰仁城跡(世界遺産・史跡) ‐沖縄県国頭郡今帰仁村‐今帰仁城(なきじんじょう)は、琉球が中山に統一される前の「三山鼎立時代」には山北(北山)王の居城でした。中山が三山を統一した後には、琉球王府から派遣された監守という役人の居城でした。しかし1609年薩摩軍による琉球侵攻で、城は炎上したとされています。監守が住まなくなって以後は拝所とし、精神的拠り所として広く県内から参拝者が訪れています。城は、外郭を含めると7つの郭からなり、その面積は首里城とほぼ同規模で、城を囲む石垣は地形を巧みに利用し、曲線を描いた城壁のディテールは美しく、沖縄屈指の名…
2024.2.20 歴史コラム 中山道 追分宿 ‐長野県北佐久郡軽井沢町追分‐上野と信濃の国境、碓氷峠の西に位置する浅間三宿は、中山道を行く旅人たちにとって重要な宿場町でした。東から軽井沢宿、沓掛宿、追分宿で追分宿で北国街道と中山道が分岐していました。軽井沢は、明治時代に入ると別荘地として有名になりましたが、開発に伴い当時の宿場町の痕跡は消え去り、僅かに残された遺物から当時の面影をしのぶ程度になっています。追分宿は中山道と北国街道との分かれ道で交通の要衝でもあり、旅籠も茶屋も多く、三宿の中でも大いに賑わった場所でした。旧街道には分去れの碑、一里塚、高札場跡、石仏な…
2024.1.20 歴史コラム 出島和蘭商館跡(国指定史跡) ‐長崎県長崎市出島町‐日本が鎖国していた時代、長崎が海外に開かれた唯一の場所でした。出島は寛永13年(1636)に築造され、安政6年(1859)にオランダ商館が閉鎖される218年間に渡り、西欧に開かれた窓口として、日本の近代化に大きな役割を果たしました。築造当時は岬の先端に扇形に築かれた人工島でしたが、明治時代以降長崎港の埋め立て等、改修・改良工事が度々実施され、出島の当時の姿は失われてしまいました。大正11年(1922)、高島秋帆旧宅、シーボルト宅跡、平戸和蘭商館跡とともに、長崎県で初めて国の史跡に登録され…
2023.12.20 歴史コラム 端島-軍艦島(世界遺産) ‐長崎県長崎市高島町‐通称軍艦島の名で呼ばれる端島は、長崎港の18Km沖合の海底炭鉱の島で、明治から昭和49年の閉山まで炭鉱の島として栄えました。もともと小さな岩礁でしかなかった端島は、度々の埋め立てで拡張し、南北約480m、東西約160m、周囲約1,200m、面積約65,000㎡となり、周囲は岸壁で囲まれました。当時としては珍しい高層鉄筋アパート、学校、病院、映画館など、生活に必要な諸施設が建ちならび、その外観が軍艦「土佐」に似ていたことから「軍艦島」呼ばれるようになりました。平成27年(2015)「明治日…
2023.11.19 歴史コラム 音羽山 清水寺(国宝・世界遺産) ‐京都府京都市東山区清……清水寺(きよみずでら)は、北法相宗の大本山の寺院で、山号は音羽山、寺の建つ地が音羽山です。開創は宝亀9年(778)、平安京が開かれる以前から創建された歴史ある寺院の一つです。音羽山の断崖に建つ清水寺の本堂は、寛永10年(1633)徳川家光の寄進により再建された木造建築で、本尊の千手観音菩薩をお祀りしています。大きな慈悲を象徴する観音さまの霊場として、古くから庶民に開かれ幅広い層から親しまれ、古い史書や文学のなかには、多くの人々が清水寺参詣を楽しむ様子が描かれています。境内には、国宝と重要…
2023.10.20 歴史コラム 奈良井宿(重要伝統的建造物群保存地区) ‐長野県塩尻市奈……奈良井宿は、中山道六十九次の中で、東海道と共有する草津・大津宿を除いた板橋から守山まで中山道六十七宿中、どちらから数えても34番目に位置する丁度真ん中の宿場町です。木曽十一宿の中では最も標高が高く、難所の鳥居峠を控え、多くの旅人で栄えた宿場町は「奈良井千軒」と謳われました。町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、往時の面影を色濃く残しており、観光名所としても知られます。
2023.9.20 歴史コラム 霊場恐山 -青森県むつ市田名部宇曽利山-本州の最北の地、下北半島にある恐山には、日本三大霊場の一つ「恐山菩提寺」があります。本坊はむつ市田名部にある円通寺で曹洞宗の寺院です。恐山は今からおよそ1200年前、天台宗の慈覚大師円仁によって開かれました。地蔵菩薩を自ら彫り本尊としたと伝えられます。火山ガスが噴出するこの一帯は、岩肌が露出し独自の景観を作り出し地獄に、一方、宇曽利山湖と白い砂浜は極楽になぞらえられ、天国と地獄の境目を表す祈りの場となっているそうです。恐山は死者の集まる山とされ、恐山大祭では、イタコの口寄せが行われることで…
2023.8.20 歴史コラム YOKOSUKA軍港めぐり -神奈川県横須賀市本町-li-->横須賀は、幕末から日本海軍の軍港として発展してきました。横須賀本港と長浦港は、米海軍と海上自衛隊が利用しており、多くの艦船を間近に見ることができます。どんな船が停泊しているかはお楽しみです。運が良ければ、米原子力航空母艦が見られるかもしれません。海風をうけながら軍港をめぐるのは、ことのほか気持ちが良いものです。望遠レンズを付けたカメラを構える軍艦ファンも乗船していることでしょう。軍港巡りの後はどぶ板通りでハンバーガーや海軍カレーを楽しめます。